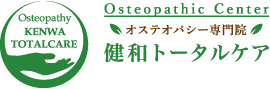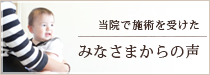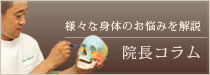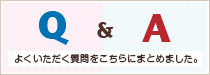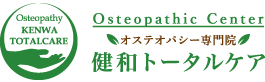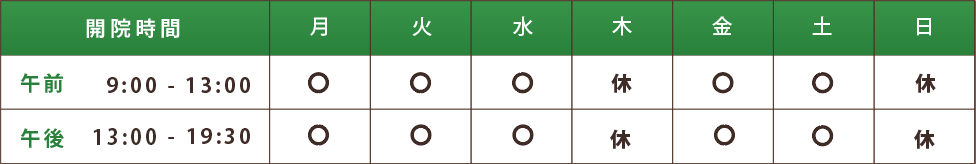2015年4月以降、愛知県名古屋市と滋賀県彦根市の二か所で開院予定。滋賀県彦根市では開業8年目。
新年、明けましておめでとうございます。
2015年は私にとって、
引っ越し、移転、第二子の出産など、
本当に大きな変化がある年でした。
また、新転地、名古屋でも多くの方にご愛顧頂き、 感慨深く想っています。
私は今37歳なのですが、
そこからこれだけの大きな変化に臨む時、 すごく勇気がいりました。
ただ、今は、『変化』に踏み出して良かったと思っていますし、
改めて、どこに行っても人に必要とされるオステオパシー施術家であるため、
さらに精進していきたいという想いを強く抱きました。
治療家という役割、仕事は、 探究すること自体が仕事の内だと常々思っています。
なぜなら、人体や人そのものが宇宙の神秘が具現化した存在であり、
知れば知るほどその深みもまた理解され、
その探求に終わりは無いと思われるからです。
そもそも、1人の『人間』に対峙した時、
本当に多くの要素が今現在の症状やお悩みと関わっていることがあり、
オステオパシーの探究には、解剖学などの基礎医学だけでなく、
人間そのものについて探求する必要があると思っています。
皆さまのお力になれる様に、 さらなる努力を重ねていく所存です。
2016年も、何卒、よろしくお願い致します。
 院長コラムでも書かせて頂きましたが、
院長コラムでも書かせて頂きましたが、
2015年11月5日(木)の3時頃に施術者の第2子の男の子が生まれました。(笑)
予定日より数日早いですが、大きさは3070グラムありました。
まあ、妻の体の大きさなどを考えるとよくここまで大きくなったなと思います。
今回の出産は前回と同様、助産院で産ませて頂きました。
お世話になったのは、名古屋の天白区にある天白助産所です。
とても安心感のあるベテラン助産師さんで、
また、オステオパシーにも理解を示してくださり、
「なんでもやってください!!(笑)」と、
出産の真っ最中もオステオパシー施術をしてもよいという許可を得ておりました。
実は、そうしたことは海外などでは珍しいことではないのですが、
日本においてはあまりない状況ですね。
今回は、お産中も妻の仙骨(骨盤の真ん中の骨)から胎児と産道の位置関係を手で感じ取り、
胎児が産道を通りやすい様にバランスを取り続けていたんです・・・。
出産前のオステオパシー施術は何度となく患者さんに対しても妻に対しても行ってきましたが、
お産の真っ最中に施術をするというのは初めての経験でした。
しばし妻と助産師さんと僕と胎児(赤ちゃん)との、
何とも言えない時間が流れていました。
そうすると、赤ちゃんもあれよあれよと子宮口に降りてきて、
あっという間に第4回旋までいきましたね・・・。
本当に、どこで躓くということもなく、驚くほどの安産で助産師さんもびっくりしていました。
陣痛が来てからすぐにCV4という第4脳室と脳脊髄液の施術を妻に行いましたが、
それも良かったのかもしれません。
赤ちゃんが出てきて産声を上げた時には、胸をなでおろしました。
また、私が一番最初に赤ちゃんを取り上げ、
妻のお腹に載せました。無事に産声も上げていましたが、
しばらくしたらまた、お母さんのお腹の上ですやすやと安心した顔をしていました。
また、私が臍の緒の拍動が止まるのを確認してから、
臍の緒を切らせて戴きました。
本当に、安らかな出産・出生経験だったと思います。
第1回旋(顎を引き骨盤入口部に嵌入)
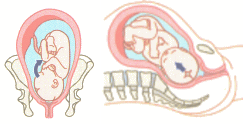
第2回旋(約90度回転しながら産道を下降し、児背が母体の前方を向く。)
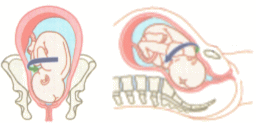
第3回旋(反屈しながら胎外に頭が現れる)
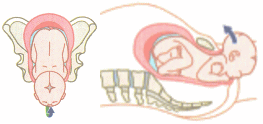
第4回旋 (回転して肩を出しながら横を向き、娩出される。)
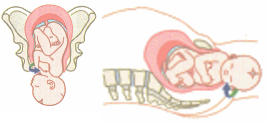
参考資料【病気が見えるVol.10:産科 医療情報科学研究所より】
結局、陣痛が最初に来てから1時間半で胎盤娩出までいきました。
1人目の子も4時間半と、初産にしては早く安産でしたが、
それを上回るスムーズさ・・・。
もちろん、オステオパシー施術は充分に行っていましたが、
やっぱり出産や出生はドキドキしますね。(笑)
本当に、妻と赤ちゃんにお疲れ様という気持ちです・・・。
また、妻子共に健康状態が良好だったので、
上の子(3歳)が退屈しない様に産んだその日の内に退院となり、
自宅療養しつつ、その後は助産師さんに訪問して頂くこととなりました。
本当に、夫としても、父親としても、オステオパスとしても嬉しく思います。
出産から3週間以上経ちましたが、
あれだけ安産だったのにそれでも息子の頭蓋を調べてみると、
若干の硬膜の緊張と軽度の向き癖が見られたため、
非常に優しい方法で調整し、硬膜の緊張を緩解させたことで向き癖も軽減されました。
正直、こうした向き癖が長期化すると斜頭を強く形成することがあるため、
早期施術が望ましいことを経験的に知っていたので、
我が子で改めて新生児の施術と研究をしているところです・・・。
小児の発達や産後の女性の体に関しても、
妻子からも改めて学ばせて頂こうと思っています。(笑)